■副島隆彦華僑が日本をつくった
天 皇 と 華 僑
聖 徳 太 子 は 蘇 我 入 鹿 (そがのいるか) で あ る 」
副島隆彦 著
(編集部によるイントロダクション)
日本は原住民である倭人(わじん)と交易を求めてやって来た華僑(中国人)が年月をかけて混血してゆくことによって出来た王国である。西暦776年に「近江令」(おうみりょう)の中に初めて出現した「日本」という言葉をもって日本建国の年と考えるべきである。従来の日本歴史学を統合する「属国・日本史論」の古代史編をここに始める。
(はじまり)
私は日本史についても調べて書きたいと思っていた。
私がこれまで考えてきた日本通史の概要のうち、ここに掲載する古代に関する部分は、一九九七年五月に五月書房(ごがつしょぼう)から刊行された『属国・日本論』のために書き下したものである。ところが、「著者を守る」という理由で、出版社側の判断により、この古代史の部分は、採用原稿から削除されため、発表の場を失っていた。今回、オルタブックス編集部の依頼により、単行本用に書いた原稿に若干の加筆をし、ここに初めて発表するものである。 1997年9月 副島隆彦
拙著、『属国・日本論』の第三部「属国日本の近代史」で私は、古代から中世、近現代に至るまでの日本の歴史を、日本はじつはずっと文明の周辺属国(トリビュータリー・ステイト)であったのだ、という観点から祖述しようとした。しかし出版社側の判断によって実際には近現代史の部分しか掲載されなかった。祖述(expound イクスパウンド)するとは、特定の先人の学説を受け継ぎ、それを土台にして更にその上に自説を展開して、同じ諸事実に対して別の角度から光を当てて自説として、そのことによって学問(サイエンス)(=科学)を推し進めることをいう。
私の日本史学についての知識は、きわめて限られている。私は日本史学者ではないので、専門的な歴史資料 ( 一次資料としての古文書や国家外交文書 ) の 古代漢文のまま読み込みや正確な文献読解 ( text critic テキスト・クリティーク )などはできない。そのような学問的な訓練は受けていないし、また、フィールド・ワークとしての歴史学を志したこともない。自分の人生時間をその領域に投入しようと思ったこともない。
それでも 私は、「属国」日本論という大きな観点からの日本通史 ( 古代から現代まで通して叙述した歴史 )を 概略、俯瞰的な 全体像として呈示せねばならないと思ってきた。それは日本人の誰かがやるべきだったのに誰もやっていないと長年強く感じてきた。
私の考えは、日本が紀元前後からの丁度、二千年間は中国歴代王朝の藩国・冊封国であったとするものだ。そして、150年前のペリーの黒船来航直後は、アメリカの属国になりかけたが、アメリカ国内での南北戦争(ザ・シビル・ウォー)の勃発で、アメリカの日本支配が一時停止した。その間に、西欧列強(ヨーロピアン・パワーズ)の中の最大の大国であったイギリス(当時は、大英帝国 The British Empire である) の属国を続けた。その後、1945年8月の第二次世界大戦での敗戦の後は、アメリカ合衆国の属国なって現在に至る。これらの大柄な日本歴史の基本性質を、歴史上の諸事実(ヒストリカル・ファクト)に照らして、大胆に叙述していくことが私の日本思想家としての構えである。
むろん、私の日本史論を素人の仕事だと無視するのはいっこうにかまわないし、私の説 ( 歴史事実への別な光の当て方 ) の細かな誤りを指摘して反駁して下さることも自由である。私は明らかな事実であることでそれが周囲の事実との関係でほぼ確実に明らかであるとされることに対してはすべて認める、という態度を取る。私は要らぬ隠し立てをする態度は一切取らない。ただ勉強時間不足の為に自分が知り得なかったことで新たに知ったことでそれが事実であることの自然な推論が立つことは、すべて認める、という姿勢である。
私の説は、「属国としての日本通史」という従来とはまったく別の観点に立ち、かつ、「世界史の一部としての日本史」という太く大きい一本の柱に貫かれているのであって、この「属国」日本という視角は、十分に学問(=科学)的な条件を備えたものであると考えている。もし私への反論があるなら、同じく、世界史の一部としての大柄な日本論であってほしい。
日本をつくったのは華僑である
歴史学とは、近代学問における定義上の重要事実であるが、文字、すなわち刻文その他の文献があって初めて成り立つものである。文献考証とその意味づけからしか歴史学は出発しない。文字の使用以前の段階にある新石器時代 ( ネオ・リスィック)の土器や遺構は、考古学(アルケオロジー)の対象であって、古代史学の対象ではない。
歴史学は、文字の有無によって先史( prehisitoric プレヒストリック ) と 古代 ( ancient エインシャント )に分けられるのである。これが世界基準での学問区分である。青森県の三内丸山(さんないまるやま) 遺跡 佐賀県の吉野ヶ里(よしのがり)遺跡の発見があって、いわゆる 縄文文化の見直しが盛んだが、あれらの遺跡からは文字や文献は発見されていないのであるから、そうした遺跡に対して「高度な文明」などという不正確な言葉を使ってはいけない。
残念ながら、日本には「文明」( civilizaiton シビライゼイション ) の発祥はない。文明と呼べるのは、東アジアでは「黄河文明」だけである。「日本文化」 Japanese culture ジャパニーズ・カルチャア はある。異様に研ぎ澄まされた神経質とも言える日本の固有の文化はある。 これは紀元五、六世紀以降になって、東アジア古代文明=黄河文明の東端としての、日本諸島に、黄河・揚子江文明の影響の下に出現したものとしてしか語りえないはずである。
先史・古代の日本に、中国を超えるような文化は存在しない。中国にはすでに六千年前に文字・文献が出現しているが、日本に文字が出現するのはやっと紀元四、五世紀のことである。
ところで、日本に文字をもち込んだのははたして何者なのか。これまでの歴史の教科書では、「大陸や半島の戦乱を逃れて渡来してきた人々によって漢字がもたらされた」などという記述がなされてきた。「渡来人」とは韓半島人(朝鮮人や朝鮮という言葉は、私は使わない。理由は後述する)、あるいは北方遊牧民族( 「騎馬民族」などとおかしな言葉を使い「騎馬民族=天孫降臨族による日本征服王朝説」を言う江上波夫というヘンな学者もいた ) のことだとされるが、これもおかしい。
当時の韓半島には、日本と同じでまだ国家の形成はない。だから朝鮮人や韓国人の渡来という考えはおかしい。 渡来人 ( 帰化人 )とすべきは、紀元一世紀前後(漢の帝国の時代 ) ごろから日本にやって来るようになった古代中国人たちのことである。
彼ら渡来人=中国人のことを正確に言えば、それは、「華僑」( overseas Chinese オーバーシーズ・チャイニーズ ) の人々のことである。
だから 「属国」としての日本の歴史は、丁度、今から2000年前の、紀元前後の頃に栄えた漢帝国の時代に始まる。この時期に、中国から商人たちが日本を訪れるようになり、現地人である倭人と交易を始めている。この中国人の商人たちはおそらく、日本に鉄鉱石や銅鉱石あるいは ひすい、めのう などの貴石の原料を交易船を仕立てて頻繁に買い求めに来たのだろう。毛皮商人でもあったかもしれない。人間が海外にまで渡ってゆく動機は、戦乱に追われて移動してゆく、というこれまでのイメージで考えるのではなくて、やはり商業活動=利益行動としての貿易を中心に考えなければならないはずだ。ユダヤ人という商業民族が新天地に、他の誰よりも早く入って行くのだが、それもほとんどは、原住民との毛皮交易ではなかっただろうか。
海外にまで進出した中国商人たちは十九世紀以降、東アジア各国 ( あるいは世界各地 )で 「 華僑 」 と呼ばれることになる人々の祖型である。そして彼ら 華僑 が、七世紀に日本という国家を建国させる原動力になっていく。
これから私が書く考えの多くを、岡田英弘(おかだひでひろ)東京外語大学名誉教授の学問に負っている。 岡田教授は モンゴル学( アルタイ学 Altaic studies アルタイック・スタディーズ ) の日本における 権威である。ユーラシア(ユーロ・アジア)大陸全体をまたがる世界規模の人類史を研究し、その一部としての東アジア研究として、モンゴル史を中心に東アジア文明全体を対象に研究しているきわめてスケールの大きな学者である。
アルタイ学という学問に従うならば、フィンランドもハンガリー(マジャール人)も、トルコも、チベットも、アルタイ語族に属する民族である。今の中国東北部(満州、南シ)ベリアに発祥したとされる、ウラル・アルタイ語族系のツングース、満州族、モンゴル族、あるいは、トルコ族(トッケン族、ウイグル族など多数)を含む大きな概念が、アルタイ学である。
岡田教授の 『倭国』 ( 中公新書、一九七七年刊 ) と 『世界史の誕生』(ちくまライブラリー 、一九九二年) そして『日本史の誕生』 ( 弓立社、一九九四年刊 ) の三冊に、私は非常に大きな影響を受けた。とりわけ 『日本史の誕生』 は衝撃的な本であった。私はこの本によって、日本という国の成立から現在に至るこの国の運命について、ほとんどの全体理解ができたと思っている。この本の出現によって、日本の古代・中世史の学問はすべて塗り替えられたと言っていいと思う。
『日本史の誕生』における岡田教授の主張をひと言で言うならば、「日本をつくったのは華僑である」ということである。このことを証明していくためのすべての学問的な作業は、『日本史の誕生』で完結している。本書をぜひ一読されたい。日本の歴史学をすべて覆す、きわめて重要な本である。
卑弥呼に 「親魏倭王」 ( しんぎわおう ) の称号が与えられた理由
岡田教授の大きな業績のひとつは、邪馬台国論争に、おそらくほぼ決着をつけたことである。最近でも次々に出土する刀剣や鏡の刻文から邪馬台国(やまたいこく、あるいは、やばだいこく ) 畿内説が強まっているように喧伝されている。しかしそれらはやがて崩れるだろう。岡田教授は、「魏志倭人伝 」 が描く邪馬台国の地理的な矛盾を、当時の中国大陸における政治権力闘争の実際から、鮮やかに解明してみせた。
以下に、岡田学説が描く三世紀のアジア世界を要約して、そののち 邪馬台国 に話をつなげよう。
西暦一八四年の「黄巾の乱」で漢帝国の秩序が崩壊すると、中国は魏・呉・蜀の三国が鼎立する三国時代を迎える。この三国時代に続く、晋(しん)の武帝の命を受けて、蜀の亡命知識人である陳寿(ちんじゅ)によって正史として書かれたのが『三国志』(二九七年に成立)である。この『三国志』は、はるか後世の明(みん)の13世紀に成立した講談本である『三国志演義』(羅漢中=らかんちゅう=作、中国四大奇書のひとつ) とはちがう。『三国志演義』は、正統の歴史書である『三国志』の内容を原型にした読物であり、『三国志』の方は、中国のきちんとした中国の王朝の交替を描いた正史「二十四史」の中の一冊である。
この『三国志』は、その性格上、当時の韓半島を制圧した晋(しん)の建国の祖である司馬イ(しばい)の業績をフレームアップし、この司馬イ(しばい)のライバルで、西域に覇をとなえた武将・曹真(そうしん)の業績を割り引くという政治的な役割を負わされていた。これが、『三国志』全六十五巻のなかに「烏丸(うがん)・鮮卑(せんぴ)・東夷(とうい)伝」があるのに、それよりもはるかに重要なはずの「西域伝」がない理由である。
そしてこの「三国志の中の烏丸・鮮卑・東夷伝」の中のわずかな一部であるのが、我が日本国(当時はまだ、「倭」の国である)が登場して描かれている「魏志倭人伝」である。「魏志倭人伝」のことは今の日本人にはよく知られている。何故なら中学、高校の歴史の教科書の中にも出てくるからである。
当然この「魏志倭人伝」にも、その記述のなかに、さまざまな政治的思惑が混入していると考えなければならない。この重要な事実を、これまで日本史学者たちは誰ひとりとして指摘できなかった。岡田英弘が世界史全体の規模から見た東アジア史を構築して、更にその一部分としての日本史を誕生させることによってこの事が可能になった。
魏の明帝の時代の二二九年に、曹真(そうしん)は西域の小帝国であった大月氏(だいげっし)から使者を迎えるという大きな成果を挙げた。
( 副島隆彦注記。 正史『三国志』と『三国志演義』との史実と事実描写の食い違い等について、あまり研究している人がいないようだ。私は、今回それをやろうと思ったが、それでは、聖徳太子=蘇我入鹿 論 に入れなくなるので、後日、正確に調べて載せる。
ただし、以下のことだけは、注記しておこうと思った。『三国志演義』の中で大変な悪役として描かれている曹操(そうそう)が、後の魏の高祖となった人物だ。その子、曹不が魏の建国者だからだ。吉川英治の『三国志』でも大変な悪役として描かれている人物である。三国時代をつくる、劉備元徳と曹操と孫権の三人とも、どうも西暦184年の黄巾の乱の時に出現した農民反乱者の中から頭角を現した人物のようである。221年に劉備が、蜀(今の四川省)で皇帝を名乗っている。諸葛亮(孔明)がその宰相になっている。それに対して孫権は呉王であるが、222年に「黄武」を名乗り、のち、228年に、南京(建業)で皇帝を名乗った。
『三国志演義』は、劉備を主人公にして、正義の人として、全編、悪役・曹操と戦う物語だが、三国時代とは、この後に続く、五胡十六国 と呼ばれる時代も入れて、3世紀から6世紀にかけて中国が不統一のまま乱れていた時代だ。実情としては、どうも北魏(帝国)を名乗った鮮卑族が、華北一体もほとんどは支配していた、ようである。始めから、「中原の覇者」も居なければ、「漢民族」などというものも存在しないようである。
この視点も岡田学説である。 副島隆彦は、もう一度、これら全てを調べて、平易に書かなければならない。2002年8月31日記 )
岡田英弘によると、次のようになる。
紀元2世紀の当時の中国で、大月氏と呼ばれていたクシャン国は、二世紀の半ばになって、仏教の保護者として有名なカニシュカ王の時代に、東西トルキスタンからアフガニスタン、パキスタン、北インドの平原にまで至る大帝国を建設し、ガンダーラ美術を花開かせた。このカニシュカ王の孫にあたるヴァースデーヴァが、曹真の働きによって魏に使者を遣わせた大月氏王の波調(はちょう)である。このような由緒ある帝国から友好使節を迎えたということで、魏の明帝は最大級のもてなしをし、波調に対し「親魏大月氏王」の称号を贈った。
ところが、こうなると、魏の明帝は、重臣である曹真のライバルである司馬イにも同じような業績を与えなくては権力のバランスが保てなくなる。こうして二三九年に、司馬イの管轄する韓半島のさらに南の東夷から女王・卑弥呼の使節団が来ると、司馬●(イ)の名誉職への棚上げを画策した曹真の息子・曹爽(そうそう)は、卑弥呼に「親魏倭王」の称号を与え、司馬●(イ)の面子を立てるという政治的配慮をしたのである。
邪馬台国は、下関周辺にあった
岡田英弘によると、以上が当時の東アジア世界である。よく知られているように、「魏志倭人伝」に書かれている通りに「陸行・・・日、水行・・・日」と、邪馬台国への道程をそのまま忠実に当時の速度でたどれば、邪馬台国の位置は今のフィリピンとハワイの中間あたりになってしまう。しかしこれは、『三国志』を書いた陳寿が邪馬台国の正確な位置を知らなかったのでも、暗号で記したのでもない。陳寿の記述する邪馬台国への道程は、魏からクシャン国への道のりとほほ同じである、と岡田教授は、資料から解明している。同様に、戸数「五万余戸」とされる邪馬台国の規模も、クシャン国の夏の都ベグラムにほぼ匹敵する。
つまり、司馬●(イ)の業績を顕彰するという目的を負わされた陳寿は、東方に大月氏国に匹敵する仮想の帝国を創造しなければならなかったのである。したがって「魏志倭人伝」の描く邪馬台国は、魏帝国からの距離と同様に、その規模もまた大幅に割り引いて考えなければならない。邪馬台国は、われわれの想像とは異なって、実際にはわずか数百戸の集落でしかなかった可能性が高いからである。紀元3世紀の当時のわが国の集落の様子を想定してみるとそのようにならざるを得ない。
このように、中国の政治史のリアリズムから「魏志倭人伝」を読み解く岡田教授の試みによって、これまで謎とされてきたことのほとんどが解明された。では、肝心の邪馬台国(やばだいこく)はどこにあったのか。
岡田教授が『日本史の誕生』で大胆に提案した説によれば、当時の倭国の国々の配列が「魏誌倭人伝」の記述どおりであったとすれば、邪馬台国の場所は、いまの下関市あたりである。下関は江戸時代には赤間関(あかまかん)とも馬関(ばかん)とも言った。「下関戦争」のことを「馬関(ばかん)戦争」とも呼ぶ呼称の中に残っている。
下関は、日本地図を概観するとわかるとおり、本州の中では、韓半島や上海に一番近いところにある。下関は、長崎から回ってきた船が瀬戸内海を通って難波(大阪)の港に入るのにどうしても欠かすことのできない重要な位置にある。九州の中心が太宰府(福岡)だったのに対して、下関は大陸に向かって開いた本州の窓口である。そして天然の良好である。この事実は極めて重要である。
「魏志倭人伝」に記された倭国二十九ヵ国のうち、対馬国、一支国から先の四ヵ国が北九州沿岸にあることは、ほぼ異論がない。邪馬台国は八ヵ国目で、二十九ヵ国目が「女王の境界の尽きるところ」とされる奴国、その南に狗好国が位置する。岡田教授は「魏志倭人伝」の記述を、交易船が北九州沿岸に沿って航海を続け、関門海峡から瀬戸内海に入り、さらに東に進んで難波(大阪)に至る道程と考えた。邪馬台国の勢力範囲の東端である奴国は難波に位置し、対立する狗好国は紀伊国にあたる。だとすれば、邪馬台国の位置は、九州と難波を結ぶ交通の要衝である下関近辺となる。卓見である。
むろん、現在の下関周辺を掘り返してみても、邪馬台国の遺跡などは発見されないだろう。先に述べたように、邪馬台国は私たちが考えるような大規模なものではなく、華僑の居留地を中心にした集落(海辺の環濠集落。インディアン砦)のようなものだったろうから、人々の期待に応えてくれるような遺跡など残ってはいないのである。
華僑の居留地の周りにできた集落が国になっていった
戦後の日本古代史学を呪縛し続け、私たち一般読者層までも巻き込んだ、あの「騎馬民族征服王朝説」の江上波夫・東京大学名誉教授の学説は、五年ほど前に一拠に瓦解・消滅した。「騎馬民族=天孫降臨族説」は、佐原真・歴史民俗博物館教授(以前は奈良の橿原(かしわら)考古学研究所・研究員)によって、『 騎馬民族は来なかった 』(NHKブックス、一九九〇年)その他の著作のなかで、完膚なきまでに打ち破られた。「騎馬民族」などという学問上の名称はそもそも存在せず、それは遊牧民族( nomad ノウマド )のことであるが、日本にも来ていた遊牧系民族は、馬や牛を去勢( castration キャストレーション)する技術伝統がないことなどを論拠として、騎馬民族征服王朝説を葬り去ったのである。
この「騎馬民族=天孫降臨族説 」と並んで、「 天皇家朝鮮渡来説 」も広く巷間に流布して来た。だが、この説にも多くの難点がある。
われわれ日本人は、「帰化人」「渡来人」という言葉にこれまで多く惑わされてきた。五、六世紀の古代史関係の本では、帰化人、渡来人という言葉を、そのまま「朝鮮半島から来た人々」すなわち、朝鮮人のことだと考えているのが大半である。だが、じつはそうではない。
まず、そもそも「朝鮮」という言葉は、紀元前二世紀の朝鮮国と十五世紀に李氏朝鮮国が建国したときに用いられた言葉である。英語ではKorea(コーリア)であるから、これが九三六年にコーリアを統一した高麗国(十世紀~十四世紀)の呼称であることはあきらかだ。したがって近い将来、コーリアン・ペニンシュラが統一されるときには、これを統一して、韓民族の地として「韓半島」と呼ぶべきで、朝鮮半島という言葉は消滅させるべきであろう。
「天皇家朝鮮渡来説」によれば、韓半島から日本に渡ってきた韓民族が、西日本地域を征服し、天皇家を興こしたとされる。だが岡田説によれば、「空白の四世紀」(晋末の混乱のために中国に文献資料が残されていないのでこう呼ばれる。べつに日本列島で大事件が起こったわけではない)に文字(文明)を携えて倭国に渡ってきたのは、既に紀元前後から韓半島南部に居住していた華僑たちであり、あるいはそれらとの混血した種族であるから、それ以前もそれ以後も、韓民族が大挙して日本に渡来したわけではない。
ここで古代の華僑とはどういう人々であったかについて、岡田説に従って簡単に説明する。
華僑たちは、中国と周辺の国々の間で交易を繰り返すうちに現地の良港に居留するようになり、やがて現地人の女と結婚して子供をつくる。ところがこの混血の二世たちは、中国人としての強烈な誇りを失わず、自分のことを中国人だと思い続ける。たとえ何代続いても自分たちを中国人だと規定し、現地人に同化しない。文化習俗もそのまま中国式である。ところが現地で生活する以上、話し言葉だけは現地語化していき、しだいに中国語ができなくなってくる。しかしそれでも現地語には文字や文献はないので、もっぱら中国文(漢文)の書物を読み、中国語を書く。
岡田説によれば、紀元前一世紀頃から日本に来るようになった華僑たちは、瀬戸内海沿岸に自分たちの「国」をたくさん建設した。この国というのは文字どおり口の形をしており、周囲をインディアン砦のように板や丸太で囲んで防御壁とし、自分たちはその中に居住した。現地人はそこに作物や産物を持って押し寄せ、交易を行ない、やがて華僑の砦を中心に現地人の村が生まれる。「魏志倭人伝」に記された倭国の二十九カ国はすべて、華僑との交易のために生まれたこうした集落である。邪馬台国の女王・卑弥呼が「三十余国を従え」というのは、私たちが思い込んでいるような西欧的な武力による支配服属のことではなく、中国船と交易をする際の倭人側の代表として大きな権限をもっていた代表者のことであって、周りの小国は、この邪馬台国に友好商社代表として交易の仲介をしてもらうことで恩恵をこうむっていた、という意味である。
私たちは東アジアの古代史を考える際に、西欧のイメージで武力制圧ばかりを想像してはいけない。人間が生きていくうえでは、商業(交易)=経済こそが重要だ。政治的な統治支配の形態よりもまず、どのようにその王国は経済活動を営んでいたか、を見なければならない。だから、当時の中華帝国から見れば、倭王を含めた周辺属国の国王たちは「三井物産タイ支店長」 のような立場の人々であったのだ、と岡田教授は言う。
このように邪馬台国は、華僑が大きな経済的・文化的影響をもっていた社会であった。卑弥呼が「鬼道に仕え、よく衆を惑わし」たというのは、べつに神秘的な妖術や魔法で国を支配したという意味ではなくて、三国時代の魏で流行し「五斗米道」(ごとべいどう)という宗教を奉じていた、ということである。この五斗米道は、道教と仏教が混ざって土俗化した宗教だったようだ。のちの中世の陰陽道(陰陽五行説、易学)もこれに類似していることから、この五斗米道がその後、日本の神道になっていったと考えたほうが理屈に合う。日本人の民間信仰の多くも、この五斗米道起源であろう。
平安から室町まで公式に栄えたのは仏教だが、一歩裏に回ると、陰陽道(おんみょうどう。風水 ふうすい )のほうが民衆だけでなく武家や貴族たちにさえ信じられていたようだ。これは江戸時代まで続き、たとえば東京浅草の浅草寺(せんそうじ)というのは、徳川家が京都から招来した公式には天台宗の密教寺院だが、表面のつくりは民衆がお参りする陰陽寺に変質している。
東アジア全体に浸透する華僑ネットワークとの類推
中国の歴代の皇帝は、税金の取り立てと金貸し業を直営で営む企業家としての側面をもっている。
けっしてすべてを武力で支配し服属させたわけではなくて、帝国そのものはあくまで交易と金融業で栄えたのである。当たり前である。現在の日本だって、秀れた技術による自動車や電子機器を世界中に輸出して、銀行と商社を中心に繁栄していることを考えてみればよい。日本(倭)が、西暦五七年に、後漢の光武帝からあの有名な金印をもらって「漢倭好国王」(かんのわのなこくおう)という称号を授けられたことからも、すでにこのとき中国の属国のひとつであったことは公式にもあきらかだ。
この簡単な事実さえも、日本ではなかなか正面から認めようとしない。だが、その際に、中国に直接服属したのは中国からやってきた華僑たちであって、現地人たる倭人たちは、その華僑がつくった国の周りに群れ集って住んでいただけの原住民ということであったろう。漢皇帝の金印は、当時トルキスタンにあった大月氏国に至る周辺諸国からも、同様のものが発見されている。
ここで余談だが、現在のフィリピンでも、為政者になった貴族階級であるアキノ元大統領の出身のコハンコ家のように華僑系貴族が沢山いる。スペイン統治時代以来の純系のスペイン人を気取る場合もあるが無理である。台湾の李登輝元総統も華僑の中の客家(はっか)という、建設、港湾作業、運輸、郵便業に従事する種族に人である。シンガポールの実力者(上級相)のリー・クワン・ユー氏も華僑であり、その中の客家である。マレーシアのマハティール首相も、純系のマレー人(インドネシア人もマレー人、マラヤ人)ではなくて、華僑との混血だと思われる。
岡田教授は、一九六三年のマレーシア(マラヤ連邦)のイギリスからの独立による建国との類推で、六六七年の日本国の建国を論じている。マレーシアの経済を握っているのは、いまも華僑(人口の3%とされる)である。彼らは人口としての多数派であるマレー人(マレー人が50%、インド人が20%であるとされる ) となるべく紛争を起こさないようにマレー社会に同化したふりをして、マレー人政治家や軍人たちを上に押し戴く形をとりながら、自分たちの経済支配権を安泰にしている。マハティール首相は、「ブミプトラ」(ブミとは、自分たち、という意味で、マレー人のことであり、マレー人を優先して取り扱う政策ということである)を推進しているがうまく行かないようだ。
このことは、インドネシアやタイ、そしておそらくベトナムでも同様である。これらの国々では、一皮めくれば華僑のネットワークが社会を支配している。そして何十年かに一度、現地人の華僑に対する反感が爆発して、大虐殺事件が起こって政変になる。このような人種暴動という形になるのである。ベトナム戦争終結後の1975年に、大量に流れ出したボート・ピープルというのはほとんどが中国(華僑)系ベトナム人たちである。旧ベトナム政府の高官たちは既に、その前にアメリカのカリフォルニア州のオレンジ郡に集団で亡命している。あれはしたがって、ベトナム人による華僑排撃だったと考えることができる。一九六九年にマレーシアで起きたマレー人と華僑との流血の衝突事件や、一九六〇年のインドネシアで起きたスハルト政権による華僑五十万人殺害事件( 「9.30事件」と呼ばれるジャカルタ暴動 ) も同様の性質である。
この反華僑暴動は、近年では、1997年9月にもインドネシアで起きている。アジア通貨危機をアメリカに仕組まれて、それで一気に金融危機に陥った東アジア諸国の国内では、それは民族対立、人種間抗争という形で仕組まれて噴出する。この暴動も直接には、アメリカの情報機関であるCIAが扇動したものであり、これによってスハルト政権は崩壊した。この時のインドネシアでの民衆暴動は、意図的に華僑系の銀行を襲撃して閉鎖に追い込むという形を取った。
このような反華僑暴動が、日本の六四五年の「大化の改新」にも通じる真実だと私は判断する。岡田学説を、7世紀の建国時の日本に類推すると以下のようになる。すなわち倭人の王たる天智(てんぢ)が、華僑の王たる蘇我入鹿=聖徳太子を襲撃したのが「大化の改新」である。
すなわち、「大化の改新」なるものが本当にあったとすれば、それは、現地人である倭人による、排外主義の感情に満ちた人種暴動のようなものであったろう。
それに対して、その次世代の華僑の王・天武(てんむ)が、倭人・天智派に逆襲をかけたのが六六二年の「壬申の乱」であろう (詳細は後述)。
ベネディクト・アンダーソン Venedict Anderson という、アメリカ人の東アジア学者(戦略学者)がいる。彼はインドネシアで生まれ育ったアメリカ人で、現在は WPI ( World Policy Institute = “ 世界政策研究所 ” ) というシンクタンクの主任研究員である。彼は、『想像の共同体』(’ Imagined Community ‘ イマジンド・コミュニティ)という大変優れた著作のなかで、現在のタイ王室が、じつはほとんど中国系であることを暴いてしまった。タイ政府は怒って、アンダーソンの入国を禁止している。タイにとって、自国の王室がじつは中国系であるという事実を書かれることは、最もイヤなことである。
ちなみに、アメリカのインドネシア研究学者(専門家)のことを、「インドネシア・ワーラー」という。インドネシア・エクスパート Indnesia expertsとも、インドネシア・ハンド Indonesia hands ともいうのと同じである。これと全く同じように、アメリカの日本研究学者のことを、ジャパン・エクスパートとかジャパン・ハンド「日本あやつり専門家」と呼ぶ。一昔前は、ジャパノロジスト Japanologists と言った。エドウィン・ライシャワー博士らのことである。このように世界覇権国(帝国)というのは、 属国群のそれぞれに、数百人の専門の研究学者を育ててはりつけさせるのである。幼い頃にその国で育ったとか、奥さんがその国の人である、という基本性格を持っている。
タイやべトナムが中国系の王朝を立ててきた、という事実を、のちにその国の正統の国家歴史は、必死で隠そうとする。 同じことは、イスラム諸国のスルタン(土侯)たちやロシアの皇帝(ロマノフ朝も)、それからインドのチムールやムガールの王家にもいえる。ムガール Mogul 王朝とは モンゴル人の王朝(1526年建国)ということである。彼らは、自分たちの祖先がかつて、「自分はモンゴル帝国を築いたチンギス・ハーンの末商(子孫)だ」と名乗っていたことをバラされるのがいちばんイヤなのである。建国の神話に属する歴史上の事実を、あとになっておおい隠すことに躍起になったのである。
(副島隆彦です。ここで、中断して、前編とします。今から、池袋でやる講演会に行かなければいけませんので。 後編は、2、3日中には、手を加えて載せます。Rss-K君、
どうもありがとう。)
副島隆彦拝
2002年08月31日(土) No. 1
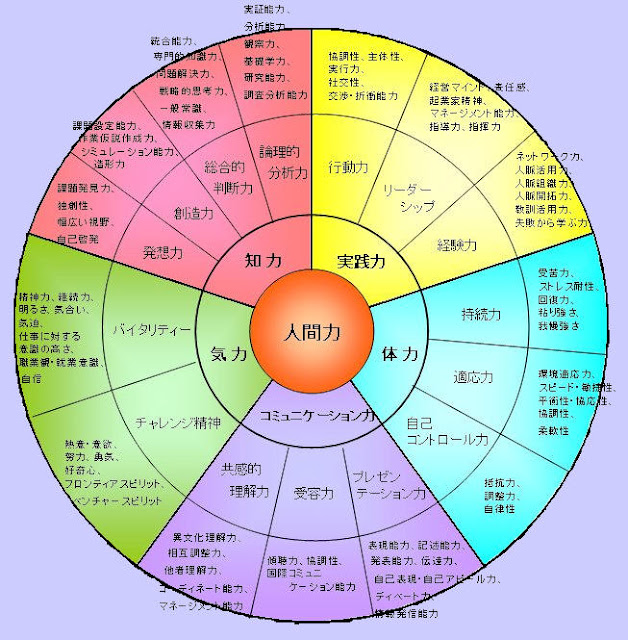


コメント