■平田篤胤・仙境異聞(2)
(引き続き引用です) 常陸国岩間山幽界 双岳山人御侍者衆中 猶々寅吉こと、私宅へ度々入来にて、深く懇志を通じ候に付、今般 下総国笹川村門人五十嵐対馬と申す者に、御山の麓まで相送らせ申 し候こと実に千載の奇遇と雀躍限りなく存じ奉り候。之れに依り憚 りを顧みず申し上げ候。尚此の上とも修行の功相積り、行道成就い たし候様、拙子に於ても祈望仕り候事に御座候、以上。」 偖また寅吉にはなむけと詠みたる歌と、其の端言(はしことば)は左に挙ぐるがごとし。 車屋寅吉が山人の道を修行に山に入るに詠みておくる、 「寅吉が山にし入らば幽世(かくりよ)の、知らえぬ道を誰にか 問はむ。 「いく度も千里の山よありかよひ、言(こと)をしへてよ寅吉の 子や。 「神習ふわが万齢(よろづよ)を祈りたべと、山人たちに言伝(こと づて)をせよ。 「万齢を祈り給はむ礼代(いやしろ)は、我が身のほどに月ごとに せむ。 「神の道に惜しくこそあれ然(さ)もなくば、さしも命のをしけく もなし。 かく記しよみ聞かせてぞ与へたりける。 寅吉が帰れる後は、心静かになりて、十日ばかりは聞き置きたる事ども書き記して在りけるに、廿七日の日に笹川村の門人高橋正雄といふ者来たれり。(字(あざな)を治右衛門といふ。)「寅吉はいかに」と問へば、「対馬と共に舟にて十九日の朝早く笹川へつきて、我が許へも対馬が伴ひ来たりて逢ひたり。彼の家に二十三日まで逗留して、対馬に咒術祈祷の事など語り聞かせ、膏薬を練り丸薬など教へて製しけるに、二十三日の夜に外より呼ぶ声の聞こえければ、寅吉きゝつけて出でけるが、暫くして家に入りたるを家僕の中に寝ながら聞きたるもあり。偖翌廿四日の朝、寅吉対馬に向かひて、『昨日の夜師の許より迎ひに遣はせたれば、今日筑波山へ参るべし』と云ふ故に、『然らば麓まで伴ひ行かむ』と云へば、『今日また迎ひ来るべし』と云ひ暫く物語などして在りしが、何気なく外へ出て行方しれず。決はめて迎ひの来つると共に登山したるべし。此の由を先生に申し給へと、対馬が云ひ遣はせて侍り」と云ふにぞ、また今更のやうに驚かれける。 斯くて童子の噂いと高くなりて、人々とよみて取々に云ひ罵るに、同じ江戸には住みつゝも、日々に来ざる弟子どもは、童子のわが家に居つるほどに来合せざる事を口をしく思へる者もいと多し。さて十一月の朔日には約せる如く、双岳山人また寅吉にも心ばかりの物を手向けて、発足の時に託せる事どもを約せる如く祈りける。然るに此の間は火事しげくて騒がしかりしが、二日の夜の七ッ時にも火事あり。家内をおこし覚まし、我も火の見に上がり見るに、本所のはてと見ゆ。其の辺には知音の人も無ければ、夜の明くるまでしばしも寝(ねぶ)らはむなど云ふ程に、門を扣(たた)く者あり。家僕を出だして問はしむるに寅吉なり。やがて小門をひらきて内に入るれば、旅ともあらぬ状(さま)にて、笈筥(おいばこ)を背負ひ入り来たるに、家内の者ども、中にも女共は鬼物には非ざるかと、恐れ惑ふもげに理(ことわ)りなり。偖「いかにして今来つる」と問へば、「笹川に行きて五十嵐氏の許に二十三日まで居たるに、師より左司馬を迎ひに遣はされし故に、二十四日のあさ伴はれて山に登りたるに、師はことし讃岐国の山周りの鬮(くじ)に当てられたる故に、寒行は休みなれば、予(かね)て申せる如く、また里に出でよとの事なる故に、古呂明と左司馬とに送られてより只今いで立ち来たれり。始めの由あればまづ美成ぬしの家にものして、呼びおこしたれど『夜は金門開けざる家の定めなれば、明日来たれ』とて入れざる故に、こなたに来侍り」といふ。「能くこそ来つれ。いかに真柱の書と手簡は見せ参らせたるか」と問へば、「先生の云ひ含められし如く申し侍れば、師は書物の事も、手紙の事も、疾く知られたる状にて、唯よしよしと云ひて点頭せられ、我が賜はれる神世文字の書をば残らず披(ひら)き見て、『よく集めたるが、中に三字云々の異体を挙げ洩らしたれば其の由を伝ふべし』と云はれたり。七韶舞の事も、『汝短笛の持ちやうを図の如く教へたるは違へり。図の如く教ふべし。舞の足ぶみも、汝は右足より蹈み出す由を云へれど違へり。左足より蹈み出す舞なり。誠に切なる志ありて問はるれば、あやまたず教へよ。また此の書に合する臥竜笛浮金をも伝ふべし』と、臥竜笛の中のしかけをも見せて、具(つぶさ)に教へ遣はされたり」と云ふ。さて何くれと山の事ども探ぬる程に夜は明けたり。 毎朝の神拝をへて、己れは屋代翁がり寅吉が来たれる由を物語りに行き、健雄は美成が許へ此の由を告げに遣(や)りぬ。そは寅吉が我がり来つる元の因(ちなみ)を思ひてなりけり。此の日来たり合ひて、寅吉がくさぐさの物語を聞きたる人々は、小嶋主、伴信友、中村帯刀、青木五郎治、笹川の正雄などなり。国友能当が仙炮の事を問ひ極めざるに、寅吉が帰山せる事を甚く歎き居つれば、また来つる由を消息すれば、五日に自作の風炮を持ち来たりて、寅吉にその仕掛(しかけ)を見せて、神炮の事を探ぬるに、相発して悟り得る事甚だ多し。此の時しも小嶋氏、屋代翁、荻原仙阿弥ぬしなど来合ひて、物語りの中に、寅吉が書を好まれしかば、今夜は多く飛白体の字をぞ書きける。然るに寅吉が兄荘吉勝手へ来たりて云ひけらく、「今日広小路名主何某の許より、我が坊の名主何某方へ云ひ遣はせたる由にて、家主をもて寅吉を連れて出づべきよし申し遣はせて侍り」と云ふ。寅吉そを聞きつけて物思ふ状(さま)なれば、屋代翁に其のよしをいひしかば、翁我に向かひて、「そは我が思ふ旨あれば、荘吉に『寅吉ことは、屋代殿より尋ね給ふ事ありて、日ごとに参れば、其の事すみて後に連れ行くべき』よし云はしめられよ」と云はるゝに、其の由荘吉に云ひ含めて帰しぬ。寅吉よろこびて「此の世の中にては、大名の門番と名主、家主ほど恐ろしき者はなし」といふ。皆々其の由を問ふに、「我いとけなくて大名屋敷に行きたる時に、したゝか叱られ、また何某とふ者の家主に店を追はれたる事あり。然るに其の家主を名主は叱る故に門番、家主、名主ほど恐ろしき者なく覚ゆ」と云ふに、皆々甚く笑ひたりき。 偖諸々帰られたるは、亥の刻を過ぎたり。けふは寅吉ひめもす諸人の応対、また書き物をも多くせしかば、己れその背をかき撫で、「けふは疲れたらむ」と云へば、取りつきて、「蜜柑を給はれ」といふ。「幾箇ほしき」と云へば、「尻に針ある虫の名ほど賜へ」と云ふ。故に「蜂か」と云ひて八つ与へたれば、悦びて此れより思ひつきて、「手近く有り合ふ物をもて、なぞをかけ給へ。解くべし」といふ。家の者ども口に出づるまにまに云ひかくるに、声に応じて悉く解きたり。其の中の五つ六つをこゝに記す。 燭台の蠟燭 ひるの九ッ時 心はひが高い 広嶋薬鑵 草津 心は湯が出る 破れ障子 憎い子のあたま 心ははつてやりたい 砕け摺鉢 小野小町 心はする事がならぬ 人だま 神鳴り 心は光りてこわい 土の団子 断食の行 心は食ひたくてもくへぬ 狸の隠囊 押さへた盃 心はまた一ぱい またかく世俗の才も有り。かくて其の夜とく、「据風呂(すえふろ)に入れ」といふに、「なぞ面白し」とて立ちざるを、しひて入らしめたるに、唯徒(いたずら)のみして体をば洗はず出でたる故に、健雄が「烏の行水とは此の事ぞ」と戯れつゝ、逃ぐるを押さへて洗ふを、己れ見て「山人の行水」とかけたれば、「月夜」と解きたり。「其の心は」と問へば、「十五日にはえる」といふ。こゝになほ根問ひをすれば、山にて月々の行の時は、日々に湯に三度、水に三度入れども、常に身を清むる行水は、毎月の十五日ばかりなりと云ふ。此の夜のなぞどもは書きつけて、翌六日の朝たよりにつけて、屋代翁がり参らせたれば、翁もかく世間の才も有りけりと感じられけり。此の日来合ひて、問答せるは、松村平作(此は大坂人にて予が門人に成らむとてわざと大坂より来て塾中に居るなり)、野山種麿、佐藤信淵などなり。寅吉が議論の高上なるに、何れも舌をまきけり。 七日の夕つかた、屋代翁来まして、秘蔵せらるゝ、唐の則天と云ひける女王の書ける□□□□といふ帖本を寅吉に見せて、「此はいかに」と云はれしかば、寅吉ただ一枚を見て、「此は位高き女の書なり」と云ふに、まづ驚き、「年の頃はいくつばかりの時の書ならむ」と云はるれば、「七十歳前後なる時の書ならむ」と云ひつゝ、末まで手早に披き見けるが、「いづこか男子の書きたる字の交りて有りし」とて、本(もと)へ巻き返して一行を見出し、「此の行は男子の書なり」と云へるにぞ、己れは更なり、屋代翁も甚く驚かれけり。然るはまづ此の帖は、かの女王が鳥虫飛白といふ体にて、此(ここ)には屋代翁ならでは蔵(も)ちたる人なく、寅吉がかつて見たる物に非ざるを、始めて見てかく目利きたればなり。則天といふは、唐の太宗といひし王の妻なりしが、夫の死にける後に云々(しかじか)して、別に国号を建て周と云へるが、その□□□□(万歳通天)と云ひける年に、みづから書きたる書にて、其時は□十□歳の時なり。また男子のかける行なりと云へる行は、彼の国の例として云々する例にて、誠に臣下の男子のかける行なればなり。 翌八日には、小嶋惟良ぬし、屋代翁、予と三人にて寅吉を伴ひて、山田大円がり行きぬ。然るは彼の人もかねて寅吉に逢はまほしき由を、小嶋主にいひ、殊に種々珍しき器ども持ちたれば、其をも見むとてなり。此の日山田氏に集へる人々十人余りなるべし。寅吉に書を乞へば、是れまで見ざる縄を結びたる如き字あまた、篆書の如き彼の界(さかい)の字などを夥(おびただ)しく書きたり。種々の物を見るにつきて種々の物語りも出でける中に、阿蘭陀(オランダ)より来たれるオルゴオルといふ楽器を見て、「山にも見たる楽器にこれと似たるが有り」と云ひ出でたり。「此時の事 (二)巻六十五丁六十六丁にもあり」山田氏「それはいかに製れる物ぞ」と探ぬれば、下に記せる鉄の箱に笛六本を仕掛け、水をはりて肘金をまはせば、中なる水の湯となりて笛の鳴り出づる器の事を語り、此の因(ちなみ)に鉄の器に水をもり、鉄棒にてかきまはせば湯のわく器の事を委しく語り出でたりき。また此の時集へる人々の中に、臼井玄中といふ人に、山人の事を答ふ。是より屋代翁の言にて、小嶋主、予、寅吉共に桑山左衛門主へ行き、此(ここ)にても書を多く書かしめらる。屋代翁も筆とりて云々と云ふにぞ、女牛に腹をつかれたる心地したりき。 九日の日に或人(松屋がこと)来たりて云々といひしかば、寅吉きゝて云々と云へるに、其の時居合ひたる松村平作、竹内健雄、守屋稲雄、岩崎芳(吉)彦などなり。松村が此れより前にもをりをり聞ける事どもを、古郷のみやげにせむと書き記せる物あり。(此を屋代翁、嘉津間問答と名づけられたり。)十日には、今井□□(一造)(呼名を仲といふ)、伴信友、岩井中務、山崎篤利、笹川の正雄など来たりて、種々の物語りしける因(ちなみ)に云々と云へり。皆々其の大議論を感じける。此の日屋代翁より口状をそへて、倉橋与四郎主始めて来られ、易の事の咄あり云々。また印相の事を問はるゝを悉く其の形を結びて伝へ参らす。十一日にも今井仲来たる。昨日の如き議論をなほ聞かむとてなり。種々物語りあり。十二日に倉橋勝尚ぬし来られて、なほ印相の事を探ねらる。此の時に印相の大議論あり。また此の日美成が許より「岩間山の近き辺なる知人の来たれるが、寅吉の噂を聞きて逢ひたきよし云へば、いかで遣はし賜はれ」と云ひ越しぬ。やがて其の人と遣はしたれば、其の知人は咒術など行ふ人にて、美成とりもちて寅吉に種々の咒術を教へしめたる由なり。其の夜は美成が許に泊りて十三日に帰りぬ。 十四日に松村平作が大坂へ帰るに、塾の者ども短冊など書きて別れを惜しみけるに、寅吉も日ごろ親しく交はりしかば、打ちふさぎて有りしが、己れに「今急に歌をよむすべを教へ給はれ」といふ。「何事を思ひて然は云ふ」と問へば、「人々の歌よみ給ふが羨しければ、我も詠みて贈らむと思ふ」といふ。己れうち笑ひて、「歌てふ物はしか急に詠み得らるゝ物に非ず」と云ふに、「然らば短冊一枚たまへ」と乞ひて 常のしわざ大抵かくをさなく可笑(おか)しければ、来集ふ人ごとに愛しく思ふも理(ことわ)りなり。然れどわやくに徒(いたずら)なること誠に類ひなし。そは己れ思ふ旨ありて少しも逆らはず、気儘に捨ておけば膝(ひざ)にもたれ、肩に取付きて学事を妨ぐる事は更にも云はず、机前に居ては机のふちを噛み砕き、錐もて穴をもみ、筆をとりて鋒(さき)をもみ、小刀とりて硯屏(けんぺい)におく。雲根石、孔雀石など打ちかき、筆墨をけづり、すり墨をこぼし、灰を吹きたて、傍らにあるほどのもの悉く瑕(きず)をつけ、庭に出でて枝を作れる木草を折り、庭中をば、いつも素足にてあるき、高みへ上りて下には何物あるをもかまはず飛び下りて打ちこはし、また竹馬に乗りて泥に落ちたるを洗はず、席上を泥まみれとなし、張り調へて程もなき障子ふすまを引破り、小児のもて遊ぶ竹もて作れる紙(豆カ)鉄炮といふ物を自ら甚(いと)強く作り、小石を拾ひ入れてふすまを打ち破り、天井板をさへにうち抜くを、其はあぶなしと制すれば畏(かしこ)まりはすれど、直に忘れては人にもうちあて、既に健雄が物書き居たる傍らより、其の耳に小石を打入れ、大きに悩ませたる事さへ有りけり。細工ずきなる故に、彼(かれ)を作る此(これ)を作るとては、鉋(かんな)鋸(のこぎり)などの類ひを再び用立たざる如く害なひ、台所むきの諸道具まで損なひ捨てたる物いと多く、家ぬちの者どもゝ稍(やや)あぐみて見ゆれど、己が愛しむ者なれば、何事も忍び居る状(さま)なり。帯も得結ばず、くるくると回して端を挟みをる故に、誰にまれ朝ごとに帯を結び遣はすを、結び果てざるに駆出すは常の事なり。またいつも寝所より帯も結ばず、かけ出ては直に誰にても取付きて角力を取らむとて、抓(つか)み掛かる。然るにわざと負けては悦ばざる故に幾度となく投付ければ、己れが負けたるかぎりは果てしなく取らむといふ。遇(たま)にも勝つときは悦ぶ事限りなし。始めて逢ひたる人をばいつも暫く其の面をうち守りてあるが、意にかなへるは、始めて逢ひたる人へも、其の肩馬に乗りなどす。世に甚(いた)くわやくなる子をば天狗の巣立ちの如しと云ふ諺のあるは、かゝる状よりは云ひ始めけむ。 また此のほど、やごとなき御辺に時めく医師の三人四人と聞こゆるが、寅吉に逢はむとて、二人来たれる日ありき。前に来たれる医師「木村玄長悴」の何事をか問はるゝと思へるに、「身の上いかに有らむ、病難は有るまじきか」など云ふ事を問ひしかば、甚く心に合ざる状(さま)ながら、可なりに答へたるを、後に来たれる医師「太田玄達」も同じ状に、身の上の事ども、病難の事など尋ねて云ひけらくは云々といふに、答へはせずて座をたち徒(いたずら)するを、己れ傍らより心苦しく、「まづ座に居て答へ申せ」と引居(ひきす)ゑれば、止む事を得ざる状にて云々と答へて速やかに立ちて、かの紙(豆)鉄炮を持ちて打散らかし遊ぶを、「あぶなし静まれ」と制する詞の下に、過(あやま)りて柱に打当てたるむくろじ程なる小石の、それて医師の後首にぞ当たりける。医師胆を冷して手をあげて首を撫づるに、己れ堪へがたく心苦しく、其の罪を謝して寅吉を叱り退くれば、医師は苦笑ひして、「実(げ)にも噂に違はぬ徒(いたずら)なり、然るによくも養ひ置き給ふ事」と云ひて帰られき。後に云々と問へば、寅吉云はく云々と云ひき。 十七日の夕方に屋代翁がり寅吉を伴ひ行く。然るは阿部備中守殿より、近習に使ひ給ふ人、二人を遣はせて、寅吉が事を尋ね給へばなり。十六味保命酒一とくり(徳利)、百花鏡を賜ふ。二人の人たち種々の事を尋ぬるに、悉く答へたり。己れと屋代翁といたく勧めて、七韶舞を教へ、太刀かきを望みて見せつ。十九日にも屋代翁がり寅吉を伴ひ行く。然るは大久保加賀守殿より近習二人を遣はせて、寅吉を見せ給ひ、酒中花、蜜柑など賜へり。二人の人たち種々問ふを大抵は答へたり。 廿日の夕方に荻野梅塢子(ばいうし)来たりて寅吉が事を語り、「彼は是れまで神仙に使へたりと云ふこと妄説なり、熟々(つらつら)察(かんがみ)るに、怜悧抜群の者なれば、其処彼処(そこかしこ)を徘徊せるほどに聞きたる事を、幽境にて見聞きしたりと云ひ触らすなること疑ひなし」と云ふ故に、己れ云ひけらくは、「中には聞き伝へたる事を語るも有るべけれど、総ては中々然る事とは思はれず、七韶舞のこと、仙炮の事などは、かつて此の世の事とは思はれず」と云へば、荻野氏云はく、「其の事どもは皆妄想なり、怜悧なる童子には妖魔のわざにて然ること有るものなり。我も童子なりし時は、世にも神童と云ひ囃(はや)されたる程の事にて、目に見ざる事物の有り状(さま)をいひ、まだきに晴雨を知り、リク(気)トさへに見えたり。其を人の誉むるが嬉しくて、今思へば杜撰妄説もいと多く吐きたりしなり。彼の童子もその如く、人に聞きたる事を山人に習へりと云ひ触らすこと、既に我が始めて逢ひたりし時には、かつて印相の事などは知らざりしかば、悉く我が教へたるに、速やかに覚えて其の後或家に伴ひたれば、其の主人に我が教へたる印相の事を元より知れる状に委しく語れり。是れをもて此の世に聞ける事を幽境に見聞きしたる事の如く云ふこと知るべし、疾く追ひ出しね」と勧むるに、己れもやゝ心惑ひていらへもせず有りけるに、寅吉次の間にて我を呼ぶ故に、立ちて「何事ぞ」と云へば、「今こゝにて聞くに、荻野氏の言甚(いた)く心得がたし。我かつて妄談を云へる事なく、彼の人に印相の事を習へることなし。美成の許にて始めて逢ひたりし時に印相の尊き由をいひて、『彼の界(さかい)にも印相を結ぶ事ありや』と問はれし故に、『尊き由は聞かざれど、此れも世にあるわざなれば知り弁へずては事欠くる事あり、覚えをれとて教へられつ』と云ひて、彼の人の望まるゝ儘に、知りたるかぎり結びて示(み)せたるに、甚く感じて、懐紙を出して書き記し、此の後にも折々此の事を問(たず)ね、かゝる事どもをよく知れるが惜しき由にて、僧になれとは勧められしなり。此は美成ぬしの委しく知られたる事なり。然れば先生の客人なれど聞き捨てがたし、此の事明りを立てゝ恥見せむ」と、眼ざしを変へて甚く憤るを、己れは更なり、家内の者もさまざまに宥(なだ)めて静めたり。後に此の事美成に尋ぬれば、誠に寅吉がいふ如くにぞ有りける。梅塢(ばいう)のいかなる心にて、右の如く云へるにや、己れも今に心得がたくぞ覚ゆる。 廿一日に寅吉みづからリンの琴のひな形を製り終へて、屋代翁へおくり、此より松下定年の許へ伴ふ。こゝに滝川主水(もんど)とかいふ神道者来合ひたるが、あるじの寅吉に書をかゝしめ、種々幽界の事を問ふに答ふるを聞きて、尻目にあざ笑ひて、傍らの人に「高津鳥の災にあへる童子よ」といふ声を聞きて、笑ひながら「君は神職の人にや、中臣祓(なかとみのはらえ)の詞にある高津鳥を、天狗の事と思ひ、我をそれに取られたる者と思はるゝにや、我はさる卑しき物に取られたるに非ず。殊に彼の詞なる高津鳥といふは、鷲の類ひを云へるよし山にて聞きたり」と云へば、神職面を赤らめて詞なし。幽界に誘はれたるに、神と山人と天狗との差別あることを弁へざるは、すべて天狗のわざと云へば、かの神職もしか思ひ、殊に天狗を高津鳥と思ひ誤れるはいとをかし。さて家に帰れば留守なりし程に、吉田尚章が(呼名を太左衛門といふ。内藤紀伊守殿の内人にて、余がふるき弟子なり。)寅吉に逢はむとて、若き医を伴ひ来つるに居合はざれば、内の者ども出でて挨拶しけるに、其の医師も寅吉が事を探ぬるに、天狗の子とのみ思へる状(さま)にて、「鼻のさまはいかに、翼もやゝ芽ぐみ侍るにや」と云へりしかば、内の者ども答へにこまり可笑しかりしとぞ。「此の日は外も内も同じ様なる事の有りし」と、寅吉も甚(いた)く笑ひける。 廿三日に上藩(番)へ出でて目付役所へ、寅吉を我が家におく由をとどけて帰る。さるは世間に寅吉が噂いと高き故に、目付役より内意ありてなり。今日も吉田尚章が来て寅吉に逢ひて、書を望み種々の尋ねあり。此の時内藤殿の領所越後国□□にて□□□□といふ産土神(うぶすなのかみ)に□年ばかり使はれて帰されたる童子の物語あり。此は□年前に帰りたるが、産土神に習へりといふ文字を書くに、寅吉が書に似たりと云へり。後にその書二枚を人に借りて遣はせたるを見れば、実(げ)にも凡ならずぞ見えける。其の童子今は二十歳ばかりにて、生国に在りといふ。此の夜に屋代翁と美成と来合ひたり。越後国蒲原(かんばら)郡小関村、上椙六郎篤興来たれり。屋代翁寅吉に向かひて云はれけらく、「汝は病には咒術を行ふよりは、藥を用ふるがよしと云へども、我は云々」と云はれしかば、寅吉も感服したり。さて今夜も又皆様と角力を取らむと望む。酒宴の上なれば己れは更なり、翁も美成もその相手となる。 廿五日の申の時より、寅吉は兄荘吉に伴はれて、東叡山まへ広小路なる名主、岡部何某が所へ行く。然るは始め童子の噂世に高く、事を弁へざるきはゝ、甚(いと)怪しき物にいひ囃せるを聞きし故に、始めは糾(ただ)し明らめむとて、荘吉に連れ来たれと度々云ひ遣はせたるが、荘吉は其の時ごとに我が許へ来たれるを、前に屋代翁のいひ置かれたる如く、いつも云ひ遣りしかば、後には名主も呼びあぐみて、荘吉が心をとり、物など取らせていかで伴ひ呉(く)れよと、切に頼み遣はせける由いふにぞ、今日は是非なく遣はしたるなり。然れど寅吉、日ごろ名主をまたなく怖きものに恐るゝが上に、名主より荘吉に、寅吉が来る日をその前日に告げてと頼みたる由なれば、決はめて人多く集へて待るべく、そが中にいかなるをこ人か有りて、彼をなじらむも知るべからずと案じられ、其の出で行く程より、己れは岩間山の方にむきて、「彼もし人に恥見せられば、我もいと口惜しきを、いかで恥見ざるやう守り給へ」としばし祈念してぞ在りける。 然るに酉の刻すぐる頃に、寅吉怒れる状(さま)ながら又快気なる面もちにて駈け戻る。後につきて荘吉も来たりぬ。「いかに」と問へば二人が言に、「侍の袴を著けざる状なる人々、名主たちなど凡て二十人ばかりも二階に来集ひたる中へ寅吉を出だし、思ひ思ひに種々の事ども問ひつれど、例の如く何を食ひて居る、雨降りにはいかにするぐらゐの問ひにて、其の煩(うるさ)く思へるが中に、真言僧と見ゆる僧の、三衣(さんえ)を厳重に著(き)かざりたるが来たり居て、我を卑しみたる状に物言ひけるが、進み出でて印相の事に及び、何の印相はいかに結ぶぞ、某の印相はいかにと問ふ故に、山にて見聞きしたる状(さま)に種々結びて見せけるに、其を元より知りたる状に点頭するが少し可笑しく、摩利支天の印相を問ふ時に、寅吉思ひつき、わざと非ざる印相を結びて見せたるにも点頭(うなず)きたる故に、此は元より知らざる印相を、知りたる状に物する僧と悟りぬ。然るは山にて見聞きたる印相は、世の僧修験者などのするとは大かた異なるを、此の僧の知りて在るべき由なければなり。然る程に祈禱の事をも問ふを、そこそこに答へたるに、其の僧終(つい)に寅吉をなじり出て、『汝の知りたる印相はみな道家の印相なり、祈禱などの事は大かた荻野梅雨が教へたる由、かねて聞きたり。偖(さて)また汝は仏を嫌ひ神を尊むといふ事をも聞きたれど、仏ばかり尊き物なければ、神を尊ぶ事を止めて仏者になるべし、吾が元より神を嫌ひなる故に、伊勢大神宮また金金(毘)羅をさへに、したゝかに悪く云ひしかど罰あたらず、此をもて神を尊ぶは益なき事を知るべし』と云ふに、寅吉甚く怒りを起こして、自然に声も荒くなりて云ひけらく、『そこは僧衣をのみしか厳重に著飾れども、一向に事を弁へざる売僧(まいす)にこそは有りけれ。然るは先に我に印相の事を問へる故に、山にて見聞きしたる如く形を結びて見せたるに、悉く元より知りたる状に点頭(うなず)きたれど、我が結びて見せたる印相は、大かた此の世の僧修験者などの結ぶとは異にて、往古の真の状の伝はりたるを習へるなれば、足下たちの知らざる形なり。然るを道家の印相なりと云へるは舌長し。此の世にて、そこ達の物する印相は、本(もと)を知らざる世々の僧らが、次々に云へ謬れるにて、本の真の状に物する僧修験者を一人も見たる事なく、人々各々結びざま違ひて、何れを真の印相と決むべき由なきが、元にて習ひたる我が印相を、違へりと云ふは、かく人多き中ゆゑに、我をかすめて人に物知りめかさむとの心なるべけれど、今我が摩利支天の印とて結びたるは、真の印に非ず、汝知らざる事を知れる顔にもてなすが憎さに、非(あら)ぬ形を結びて試みたるなり。然るを汝うなづきたるは、真の印を知らざる事は更にも云はず、汝が輩の常に結ぶ誤りの印相をさへに知らずと見えたり。また祈祷などの事を、荻野氏に習へりと聞きたるよし、そは何者かしか云へる、先ごろ平田先生の許に、荻野氏の来て物語らるゝを聞けば、彼の人我に印相を教へたる由いへり。然れば其の辺より然る説を聞きて云へるにや。山崎美成といふ人に探ね見よ、荻野氏はかへりて我が印相を見て、返す返す問はれたるをや。偖また我が神を尊ぶ事を異見がましく云へども、仏はもと此の国の物に非ず、神は此の国の物にて、我も人もその御末なる故に、順道をたどりて、其の道を第一とすること、我が師の教へにて、これ真の道なり。汝こそは其のよる仏道の事も生知りなれば、早く還俗して神の道に帰るべし。また汝は神を嫌ひなりと云へども、汝も仏の子孫には非ず、神国に生れたる人として、神を嫌ひといふは、此の国を嫌ふ理りなれば、此の国に居らぬがよし。僧と云ふ者は、大かた汝が如く、心ひがみて穢(けが)らはしき者故に、我は元より僧を嫌ひなり。偖また天照大神、金毘羅神などを詈り奉れるに、罰当らざるをもて、神には利益なしと云へるが、神は大らかに座(ま)します故に、汝が如き穢れたる者に罰を与へ給はざりしならむ。もし誠に神はいかに申しても罰の当らぬ物と思はば、今試みに大神宮、金毘羅宮などを詈りて見よ、我こゝにて彼の宮に祈り訟へて、忽ちに御罰を蒙らせてむ』と、散々に詈りて帰り来つ」といふ。猶その末の事を問ふに、よくも答へざれば、又兄に問ふに、「我は玄関に居たる故に、委しくは知らざるが二階にてしたゝか人を詈る声きこえたるが、暫くして階子(はしご)をかけおり、玄関に出でて『帰らむ』といふ、後より家あるじと、二人三人送り出でて、『また重ねて』といふを聞き入れず、『かく不興なる家にいかで二度(ふたたび)来たらむ』と、すげなく云ひて飛ぶが如くに駈けて帰るを、吾は後より『静かに』といへど、駈ける故に追ひかけて途なる盛土につまづき、膝をかくすりむきたり。名主の所にて、寅吉が如く荒ぶる者を遂に見たる事なし。定めて後にて、我に尤(とがめ)あらむ」と舌をまきてぞ語りける。 後の事は知らねど、まづ恥見ず帰れる事を、己れも悦びて在りけるに、二三日すぎて、佐藤信淵わざと来たりて云ひけらくは、「去る廿五日の夜に広小路名主の宅にて、寅吉が甚(いた)く僧を詈りたるよし、其の席に居たる何某といふ者に聞きたり。其の人は甚く感心して語りしかども、然る事ありては、ますます人に憎まれ謗(そし)らるゝ事なれば、此の後にも然る事なきやう、禁(いまし)め給へ」といふにぞ、其はいかに聞きつると問へば、始め終りは、兄弟が言の如くにて、「彼の僧の神を詈りても罰は当らずと云へるを尤めて、『今我が前にて詈り見よ、大神宮、金毘羅神に告げて今立ち所に罰をあて給ふやう祈らむ、いざいざ』と責めけるに、満座の者ども興をさまし、甚く恐れて、僧に向かひ、『此の子は彼の界(さかい)に使はるゝなれば、いかにも祈らば忽ちに験(しるし)あるべし、出直し給へ』といふに、其の僧まけ惜しみの苦笑ひしつゝ、『しか仇をせられては迷惑なり、我も神の道を知らざるに非ず、今汝に其の道を説き聞かせたく思へども、「魔なりと云へること」 三衣(さんえ)を着ては三宝(さんぼう)に対し恐れある故に、説くこと能はず』と云ふに、ますます怒り、『いかにも然る穢らはしき物きて、神の事を申しては恐れあり、但し汝はその帰依する所の仏道をさへに能くも知らざるを、いかで神の道を知るべき、其はただ負けをしみの詞なり、もしそれ負け惜しみならずば、いかに一事も説き見よ、汝が如き売僧(まいす)のいかで誠の事を知るべきや、大勢の中にてかく云ふを口惜しとは思はざるか、いざ神の道を講釈せよ』と、返す返す責めけるに彼の僧の顔は火の如くなりて、何やらむ、くだらぬ言をつぶつぶ云ふを、寅吉なほ甚(いた)く詈りしかば、家あるじと今一人、寅吉が傍らに居たるが、すかし宥めて、『あの御僧は格式高き人なれば、然(さ)な云ひそ』と制するを聞き入れず、『僧の徳といふものは三衣の厳重なるや、寺格などによる事に非ず、此の僧あたまを丸めて、三衣は立派に著かざれど、其のよる所の仏道も知らず、況(ま)して神の道を知らずして、神を悪口し、我に恥を与へむと為たる穢らはしき坊主なれば、いかに云ひたりとも何てふ事かあらむ、大抵世の出家といふ者、俗家を欺き、物とりて衣服を飾り、寺格などにほこりて人を見下すが憎きゆゑに、我は元より坊主を悪(きら)ひなり、我が坊主を嫌ひと云ふ事は、兼ねて聞き伝へたらむに、切に我を招きつゝ、何とてかゝる売僧(まいす)をよび置きて、我に恥与へむとせられしぞ、我が師は、釈迦よりも遥か前より、世に存(なが)らへ給ふが、常の物語を聞くに、仏道といふ物は、愚人を欺きて、釈迦の妄りに作れる道なりと聞きたり。思ふにこゝに集へる人々は、大かた仏ずきの人々にて、神の道を知らざる故に、世間の訛(あやま)れる評を聞きて、我を怪しみ試(ため)さむ為に、此の坊主をよび寄せたるならむ』と云ふに、人々すまひて『然る事には非ず、彼の御僧は今夜不意に来たり合ひたるなり、まづ怒りをしづめて』と、菓物など進め、紙筆を出だして書を請ふに、常の小さき筆に半紙をそへたりしかば、『紙も筆もけちなり』と喃(わめ)きつゝ、硯に厳しく突きて深くおろしたれど、猶細く、殊に怒りの最中なる故に、能くも書かれざりしと見えて、『吾は何方へ出ても、かゝる悪しき筆もて書きたる事なし、筆のもそつと大きく宜(よ)きを出し給へ』といふに、家内に尋ねて出したるも、なほ小さけれど、其をとりて、めつたに六七枚かき散らして、『紙筆ともにあしく、殊に坊主のをる故に、今夜は不出来なり』など喃く間に、膳を出してまづ寅吉にすゝむるに、『彼の坊主が居ては穢(けが)らはしくて食(めし)もくへず』といふに、是非なく、主人をはじめ、人々かの僧に、『此の子は出家を嫌ふといふ事かねて聞きたり、貴僧のおはしては、この怒り静まるまじければ、帰り給へ』といふに、彼の僧はしぶしぶに立ちて、居(す)ゑたる食(めし)をくひもやらず、なほ捨詞(すてことば)に負けをしみを云ひつゝ、階子をおりて帰れるに、寅吉はなほも怒りの顔色とけず、世人の神道を知らず、仏道に淫すること、出家の不行状なる事など、喃きつゝ一椀の食に菜を残らず食らひて、物付きたる状に、食(めし)を九椀かへて食ひたり。人々『余りの大食なり、すぎまじきか』と云へば、『食(めし)にあたると云ふことは無き事なり』といふ。またあるじ傍らより、『何ぞ心にかなへる菜をかへて』と云ひしかば、鯛の焼物の替りを請へるには、甚く困りて、暫くして密(ひそ)かに調じたる状なり。また柿と蜜柑とを、盆に三四十ばかり盛りて出しけるに、其は彼の僧と問答の間に、謾(みだ)りにとりて皆食ひ尽せる故に、また同様に盛りて出したるに、其れをも二十ばかりは食しぬ。かくて僧と問答の間は、目はいとど大きく光りて別人の如く見えて、座中の人々冷(さ)ましく覚えしとなり。さて食事をはると、早帰らむと立上がるを、人々なほ心をとりて、『しばし』と止むれど止まらず。『かく不興なる家に長居は好まず』と云ひて、暇も請はず、階子(はしご)をおりて帰りつ」と、舌をまきて語りしと云ふに、己れも始めて其の時の事を委しく聞きて、其は決はめて双岳山人の幽より守護して然る振舞ひを為さしめたる物ならむと悟りぬ。 かくて後に、その僧は何者といふこと聞きまほしくて、此の事美成に語りしかば、美成が因(えにし)を求めて探りたるに、下谷金杉町なる真言宗の修験者、真成院といふ者にて、今流行(はや)る江戸風の仏学をものする才僧なりと言へり。さて同月廿六日寅吉が兄荘吉来たりて云はく、「名主がたにて昨日寅吉がものせる時に、機嫌を損なひて帰れる事を快からず思ひて、いかで再び伴ひてと請ひ遣はせて侍り」と云ふを、寅吉きゝて、「我決はめて彼の家へはまた行かじ」と云ふを、荘吉わびて、己れに云ひけらく、「弟がかく申す上は力無けれど、我は名主の支配下に住む者なれば、然は云ひがたし、何卒こなたの御弟子奉公にして賜はれかし、然もあらば名主より呼びに遣はせたりとも、其の由を云ひて断り候べし、然もなくては支配下の我ゆゑに、断りを云ひがたし」と云ふにぞ、実に然(さ)る事に覚えて、此の事屋代翁と議りけるに、「苦しからず荘吉が願ひの如くし給へ」と云はるゝ故に、兄より例の如く諸色まかなひ、弟子奉公の証文とりて、今まで著たる汚き服物を脱ぎ替へさせ、新しき布子、羽織袴、大小なども与へて、我が家に置く事と成りしかば、侍の形になりしとていたく悦びぬ。 さて此の夕がたに美成来たりて、「寅吉わが方に居たりしほど、大関侯の奥方の七年がほど悩まれし癪(しゃく)を、ただ一度まじなひの符を奉りつれば、直れる故に、頻りに見たく思ひ給ふ由なり。また水戸家の立原水謙(翠軒)翁も、寅吉が事を聞きて逢ひたしとて我が家に尋ねられたれば、今日伴ひたき」よしいふ故に、遣はしぬ。立原翁甚く悦び、書をも多く書かしめ、種々の事を尋ねて其の答へを感ぜられしとぞ。さて大関侯へも伴ひ、夜に入りて連れ帰りぬ。水謙翁後に、屋代翁に語られけるは、「世の生漢意(なまからごころ)なる輩は、此の童子の事を疑へども、我は幽界に誘はれたる事実を、目のあたり数々見聞きたる故に、一点も疑ふ心なし、また誘はれて彼の境に行きたるには非ねども、神仙に薬方を授かりたる者も正しく見たり。其は水戸の上町といふ坊に、鈴木寿安といふ町医の子に、精庵と云ふ者あり、今は三十歳ばかりなるが、十五六歳なりける或時に、容貌凡ならぬ異人忽然と来たりて、某の日に下総国神崎社の山に来たるべし、方書を授けむといふに、辱(かたじけな)しと諾しつれど覚束なく覚えて、其の日行かざりしかば、また或日その異人来たりて、何とて約を違へて某日に来たらざりしぞ、某の日には必ず来たれと云ひて帰りぬ。爰(ここ)に精庵不思議に思ひつゝ、約せる日の前日家を出て、神崎社の山に至れば、かの異人まち居て一巻の方書を授けて、返す返す人に示(み)する事勿れと禁(いまし)めて帰しぬ。其は○○病の薬なり、用ふるに従ひて功を成(なし)しかば、此の事遂に侯庁に達(きこ)えて、役人中より其の一巻を出だし見せよとありけるに、異人の禁(いまし)めを申したれど、聴き入られず、是非なく役所へ出だす事となりける。其の前日に家に紙の焼くるかほりす、此彼(あれこれ)と見れど知れざれば、近き辺の事ならむと云ひて有りけるに、翌日役所へ、彼の一巻を持出さむと、納めたる所を見れば、彼の方書はみな焼けて少しも残らず、殊に奇(あや)しきは、反故もて包み置きたるに、其の包紙はくすぶりたるのみにて少しも焼けず有りけり。家内大きに驚きて、此の由を申さば偽りと聞こし召さむかと、甚く心を痛めけるが、是非なく其の焦(こげ)たる包紙の反故をもち出でて右の由を訟へたる事あり。神仙の不測かくの如くなれば、寅吉童子が事は疑ふべきに非ず」と語られしとぞ。然すがに章(彰)考館の総裁とありし人とて、よくも弁(わきま)へられたるかな。 廿七日に伴信友来たりて、夜に入るまで予と共に種々の事を探(たず)ぬる。そは云々の事などなり。此の日山にて、師の夜学するに用ひらるゝ器の事に及びぬ。そは山に月夜木とて、十五六町ばかり放ち見るに、光る木あり。其を細かにして硝子を 廿九日に越後国より、戸田伴七国武といふ、己れが説を信ずる者来たり宿りて、道を問ひけるが、これいと猛き荒男にて、髪、髭は生えたる儘にて、髪をかき上げて笄(こうがい)と櫛をさしたり。其の形状を寅吉つくづくと見て、「古呂明の顔の柔和になき様なる顔なり」といふ。さて此の男国々をいはゆる武者修行にめぐりて、勝ちも負けもしたる事ども、また神主、出家などと、数々議論をも為たる咄など大音に語りけるが、腰なる提げ烟草入れを取出して、「この根付けはとある修験者と議論して、勝ちたる時に取りたる本尊の聖天(しょうてん)なるが、ろくろぎりにて穴をあけて根付けに為たるなり」と云ふ故に、己れ余りなる事に覚えて、然る英気をくじかむと、態(わざ)と手に取らず、「子はよくも然る穢き物を腰に付ける事かな、余は手にとる事は更なり、目に見る事さへ汚らはしく思ふなり。然るは古学に志を赴くる者は、まづ心に真の柱を立て、常に神の御稜威(みいつ)を受賜はるべく願ふこと故に、身体を清浄に保つべきわざなり。然れば仮初(かりそめ)にも神の悪(きら)ひ給ふ、然る枉々(まがまが)しき物など体に付くべき事に非ず。そは伊勢両宮の神事には更なり、朝廷にても重き神事を行ひ給ふをりは、仏法ざまの事を忌み蕃客の来たれる時、また其の帰れる後にも、塞(さい)の神の祭を為して蕃国の妖神(まがかみ)を追ひ退け給へる古の道を思ふべし。然るに其の古道によりつゝ、然る妖々(まがまが)しき物を身に付けると云ふ事や有るべき。さて余も覚えある事なるが、此の道に入立ちたる程は、外国々の道風なる事どもは、憎く堪へがたくて、子のやうにせま欲しく思ふものなれど、其は荒魂(あらみたま)のすさびにて、長(おさ)らしからぬ態なれば、唯々一人学問して徳行をつみ、願はくば著述をして、自然とその徳化の普く世に及ぶべく勤むる事肝要なり。子の如く荒(すさ)びて二人三人に勝ちたりとも、其の徒も決はめて心よりは服せず、返りて謗(そしり)を招くわざなり。世に一升入る陶器に一升入れば鳴らざるを、中ばに入りては鳴るといふ譬へあり、しか荒び鳴りては、其の譬へを引いていふ人も有るべし。いかで其の像を海にも川にも捨てよかし」と云へば、伴七甚く畏(かしこ)まりて、「実に辱(かたじけ)なき御諭なり、然らば此の像によく祟らぬやうに申し含めて、捨て侍らむ」といふにぞ、余も可笑しくなりて、「子はいと剛なる人と思へば、しか心弱き事をいふ。古学する者の、然ばかりの物に祟られむかと恐るゝ如き、云ふがひなき事やある。殊に其の聖天といふ物は、元より有名無実の物と思はるゝが、祈りて験ある事もあるは、妖魔遊魂のより憑きて見(げん)ずるわざと見えたり。凡て妖物は然る事あれかし、寄添はむ人の心に透き間のあらば、付け入らむと窺ふ物なり」といふ折ふし、傍らに田河利器、竹内健雄、寅吉も居たれば、「皆はいかに思ふ」といふに、利器と健雄とは、戸田に初めて逢ひしかば、聊か心をおき、唯(いら)へかねて在りけるに、寅吉は少しも心おかず、「誠に言ふ如く元より無き物と云へども、形を作りて祈り立つれば、妖魔の類より憑きて、種々の変を見ずるものぞと師も言はれたり。偖(さて)また其の像は海河へ捨つること宜からず、鋳潰すべき物なり。然るは海河に捨てたる物と云へども、遂に陸に上がる期(とき)ありて、網にかゝりなどもして上がる時は、霊像よとて、世の人は信じさわぐ物なりと云ふことも聞きたり。然ればまた後世の愚人を惑はすわざなる故に、鋳潰すに及(し)くはなし」と云へば、伴七も実(もっと)もと悟り、「然らば鋳潰して捨つべし」と云ひてぞ帰りける。 十二月朔日に塙氏の塾生佐藤甚之助来たりて、余にひそかに逢はむと云ふ。此は去年の夏より知る人なれば出でて逢ひけるに、「先頃より温故堂にて、をりをり屋代氏の言を聞くに、奇(あや)しき童子ありて、幽界の事どもを語るが、君の常に説かるゝ趣に符合の事ども多きよし聞きたり。然る事侍るか」と問ふに、「実に然る事あり」と云へば、甚之助云はく、「其の事に就きて申すべき事あり。然るは此のごろ我が神学の師大竹先生がり物しけるに、何某といふ神職の来たりて、君を散々に誹謗しける中に、幽界の事を語る童子の事も、『平田は山師なる故に教へて言ひしむる事ぞ』と云ひ、また石笛の事をも云ひて、『彼の笛は神感にて得たりなど云へども偽りなり、我が知れる古道具屋の久しく持ちたるを請ひ求めて、しか云ひ触れたる故に、其の者は甚く怒り居る』よし語るを、大竹先生聞きていたく心苦しく思はれ、何某が帰れる後に、『我は平田といまだ知る人ならねど、今の世の神の道を盛んに弘むる人とては此の人なり。然るにかるゝ悪評をうくる態ありては、同じ道をたどる我らも共に心恥かしく、且つはいと惜しき事なれば、子は平田氏と知る人なり、行きて我が旨を伝へよ』と云はるゝ故に、石笛の事はかねて承り置きたれば弁へつれど、童子の事はいまだ旨を承らざる故に、この事申さむ為に来たれり」といふにぞ、己れ形を改めて、「誠に同志の徒(とも)どちは斯くこそ有るべけれ、大竹氏の我を思ひ給ふこといと辱し、然は有れど、彼の童子は己れ元より知る者に非ざりしを、前に山崎美成が許に居る時に、既(はや)く我が説と符合する事ども云ふ由を、屋代翁の聞き出でて、我を伴ひ問答せしめたるが始めにて、今は我が許に置く事とは成りしなれば、然るねぢけ人はよしいかに云ふとも、元より知る人ぞ知るぞにて、幽(ひそ)かに恥じること無ければ、何でふ事はあらじ、此の事よく大竹氏に謝して給はれ」と云へば、佐藤氏は心得て帰りぬ。 己れは何ちふ因縁の生まれなるらむ。然るは藁の上より親の手に のみは育てられず、乳母子よ養子よと、多くの人の手々にわたり、 二十歳を過ぎるまで苦の瀬に堕ちたる事は今更に云はず、江戸に 出て今年の今日に至るまでも、世に憂しと云ふ事のかぎり、我が 身に受けざる事は無けれど、是れぞ現世に寓居(かりずまい)の修行 なれど、世の辛苦をば常の瀬と思ひ定め、志を古道に立て、書を 読み、書を著はし、世に正道を説き明かさむとするに就きては、 目に見えぬ幽界は更なり、鳥獣虫魚、木にも草にも心をおきて、 憎まれじと力(つと)むれば、況(ま)して世の人には我が及ぶたけ の、所謂陰徳をつむを常の心定めとして、人はよしいかに云ひ思 ふとも、幽(ひそ)かに恥じる事はせじと、仮りにも人の為に宜(よ) からぬ事を為たりと思ふことは無きに、上の件の如く作り言(ごと) さへして、我を謗(そし)り憎む人も多かりと聞こゆるは、いかなる 由ならむ。別に□□といふ人は、今までかつて名も面も知らぬ人な れば、憎みを受くべき覚えはなきに、然る作り言して誹ることは、 いかなる意ならむ。また此の後に上総国中原村なる、玉依姫社の神 主、弓削春彦が来て、我が許へ来ざる前にかねて知人なれば、□□ が許に立ちよりけるに、余が事に及びて、大竹氏にて云へる如く、 甚く謗りて、「『此のほど彼の童子は召し捕らへられ、平田も其の 事にて御尤(とがめ)を受けたり』と語りし故に、心ならず彼所(かし こ)より急ぎ参りつ」と、余が事なき体を見て悦びつゝぞ語りける。 彼の人のしか人ごとに我を謗り聞かすること、返す返す不審なり。 余は彼の人に罪犯さずとは思へども、道の長手に這居る小虫を、心 とはなく沓(くつ)の下に踏み過(あやま)つ事も有れば、若しくは彼 の人にもさる類の過ちはせざりしか覚束なし。もし然もあらば我過 ちけり、思ひ宥めてと人々云ひつぎ給ひねかし。此の外にも童子の 事につきて、我を誹れる人々多かる中に、「平田は自説を弘めむと して大妄説を作り、故鈴屋翁は幽界にて天狗と成られ、其の使者な る童子を遣はせて、年ごろ我が説きたる説(こと)どもの、よく幽界 の有り状に符合する由を云ひ遣はされたりと披露す、いと憎き事な り」と云ひふれ、或は「神世文字の書を著せるによりて、其の字を 真(まこと)の物にせむとして、幽界の字の事をも童子に教へて云は しむるなり」など云ひ触るゝもあり。又かゝる言を朋友弟子どもな どの聞き伝へて、然る人のさかしら故に我に思(おも)ほえざる災難 あらむかと気遣ひて、とく童子を逐ひてと勧むる人も多く、また常 に我が許に来通ひつゝも、漢意(からごころ)うせず幽界の理りをよく も心得ざるきはゝ、童子の言を疑ひ、世のさかしら言に率(まじこ) らるゝも多かるに、己れさへもをりをり心のたゆたふ事も有りしは、 実(げ)にも人の口ばかり恐るべき物はなきなり。 二日に鈴木敬貞近ごろ久しく見えざるが来たれり。(呼名を吉兵衛といひて、商人なり。)然るはこれが妻を常石(とわ)といふ、六十歳あまりなるが、老女には珍しく、夫と同じ様に元より仏道を嫌ひて神を尊み、余が説を信じて年ごろ来たり通ひ、講説を聞きたるが、性質強悍猛固なるに、決はめて美詞滑稽をもて夫の心を和らぐる才もありしかば、己れ戯れて於須女老嫗(おずめおうな)と名付けたるが、此のごろ甚く煩(わずら)ひて今をかぎりと見ゆるに、我が許に幽界に仕ひたる童子の来たり居て、種々語るを己れが信ずと聞きて、深くあやしみ、「『若しくは先生の学事の今弘まらむとするを妬(ねた)む妖魔の、然る童子を遣はせて、まづ師の旨に応(かな)ふ言を云はしめ、漸くに災難あらしむる結構には非ざるか』と、深く案じて『師に此の言を申し給へ』とて、今日わざと吾を遣はせ侍りぬ。彼が言も理りある事と覚ゆるを、いかに然る事と思ひあたり給ふ事は侍らずや」と云ふにぞ、己れ甚く感じて、「我も既(はや)くより然る心つきて、今も常に心をつけて伺ひ居れば、謀らるゝ事は非じ」とて、我が思ふ旨を委しく語り、「夢々案じ過ごすこと勿れと云へ」といひて帰しぬ。此は老嫗の言ながらも、実理に合へる物思ひなりけり。敬貞が帰れる後に、門人どもに此の事を語るを、寅吉きゝ居て、「前にも申せる如く親しく使ふる我さへに、師の邪正を知ること能はず、またかく成れる事の善きか悪しきか弁へねば、まして現世の人の然る疑ひは尤もなる事なり」と云へりき。(此の時始めて、於須売嫗が病の事をきゝて、尋ねむと思ふほどに、四日の日に死(みまか)りぬと告げ来たる。今際(いまわ)までも此のことを案じて在りしとぞ。)三日に伊勢内宮の内人、荒木田末寿(すえほぎ)神主来たる。此は己が旧相識の人なり。(常の呼名を益谷大学太夫といふ人にて、故鈴屋翁の弟子なるが、所謂旦家廻りにとて、江戸に来たれるなり。)「童子の事を、彼是にて伝へ聞きたるに、いと不審(いぶか)しく思ふを、委しく聞かむ」と云ふ故に、此ごろ筆記したる物どもを示(み)せ、また寅吉が書を物する状をも見せけるに、此れも深く感じて行きけらく。「此の童子の仕ふるは、実に神仙の正しき物と見えて、いと穏やかに聞こゆるを、山人も国所によりては荒々しく人をおどし誑(たぶら)かす事と見えたり。然るは駿遠参あたりに天狗と聞こゆるは、多く手火など燭し連れて人をおびやかすを、常のわざとして、いと憎き物なり。往(いに)し文化七年の夏のころ、由ありて僕二人つれて秋葉の山を夜行せる事ありけるに、例の如く峰より峰に手火をいと数多(あまた)ともし、今遠山に見ゆると思ふに、やがて目前に来たりなどして驚かし、又は山鳴り、大木を抜き倒す如き有り状などして、おびやかしける故に、僕らが甚く恐れて進み得ざりしかば、己れ挟み箱に腰かけ居て大音に、 安国と安らけき世に熒(かがり)なす、かがやく神は何の神ぞも と詠じて、『我は伊勢大御神の内人にて、神用にて此所を通るとは知らざるか』と呼ばはりしかば、手火も忽ちにきえ、林の動(とよ)む事も止みたることあり」と云へり。 『仙境異聞』(上)一之巻 終 | ||
(注) 1. 本文は、岩波文庫 『仙境異聞 ・勝五郎再生記聞』(子安宣邦 ・校注、2000年1月14日 第1刷発行) により、(上)の一之巻を掲げました。 ただし、本文中の会話等を示す鉤括弧(「 」『 』)は、読みやすさを考慮して引用者が付 けたもので、文庫の本文には付いていません。その関係で、鉤括弧(「 」『 』)内の読点を 句点に改めたり、会話文末の読点を省いたりしたところがあることを、お断りしておきます。 なお、<『仙境異聞』(上)一之巻 終>も引用者がつけたもので、岩波文庫にはついて いません。 2. 文庫の本文には校注者・子安宣邦氏による後注が付いていて、読むうえで大変参考に なります。また、巻末に解説(『仙境異聞』─江戸社会と異界の情報)もあります。 3. 岩波文庫の底本は、『平田篤胤全集』第八巻(内外書籍、昭和8年刊)所収の平田家 蔵本の由です。 4.上記本文の「おぼろおぼろ」「ざわざわ」「くるくる」「わいわい」などの繰り返し部分は、 文庫では「く」を縦に長く伸ばした形の踊り字になっています(文庫本文は縦書き)。 5. 寅吉の通った「岩間山」とは、茨城県岩間町にある「愛宕山」(標高305m)のことです。 岩間町は、平成18年3月19日、町村合併により笠間市になり、岩間町という町名が消 失したようです。愛宕神社の住所を検索してみると、西茨城郡岩間町泉であったものが、 笠間市泉という新住所になっていました。 6. 「篤胤歌碑」について 2001(平成13)年1月に、茨城県岩間町の愛宕山に建てられた「篤胤歌碑」については、 資料46に 岩間 ・愛宕山の 『「篤胤歌碑」について』 がありますので、ご覧下さい。「篤胤 歌碑」は、 上に掲げた『仙境異聞 』の中の、篤胤が岩間山(愛宕山)に出かける寅吉に贈っ た和歌5首を刻した歌碑です。 7. 『仙境異聞 』現代語訳というホームページで、『仙境異聞 』の全文を、現代語訳で 読むことができます。 8. 上記の岩波文庫 『仙境異聞 ・勝五郎再生記聞』に収められている「勝五郎再生記聞」 は、武州多摩郡の農民源蔵の息子勝五郎という8歳の子どもの「生まれ変わり体験」の、 同じく篤胤による記録です。 9. 平田篤胤(1776-1843)=江戸時代後期の国学者。国学の四大人(荷田春満・賀茂 真淵・本居宣長・平田篤胤)の一人。通称、大角・大壑。秋田藩士、のち松山藩士。 江戸に出、致仕して本居宣長死後の門人となる。激しい儒学批判と尊王思想が特 徴で、宣長の古道精神を拡大強化し、宣長系の正統派からは嫌われたが、中部・ 関東以北の在方の有力者に信奉され、一大学派をなした。その影響力はきわめて 強く、幕末尊攘運動に大きな感化を及ぼした。弟子に佐藤信淵・鈴木重胤らがあり、 著書に『古史徴』『古道大意』『霊能真柱((たまのみはしら)』『玉だすき』『古史伝』など 多数がある。 <角川書店『角川日本史辞典』第2版(昭和41年12月20日初版発行・昭和49年 12月25日第2版初版発行)によりました。なお、著書名その他、記述を一部引 用者が補ったところがあります。> | ||
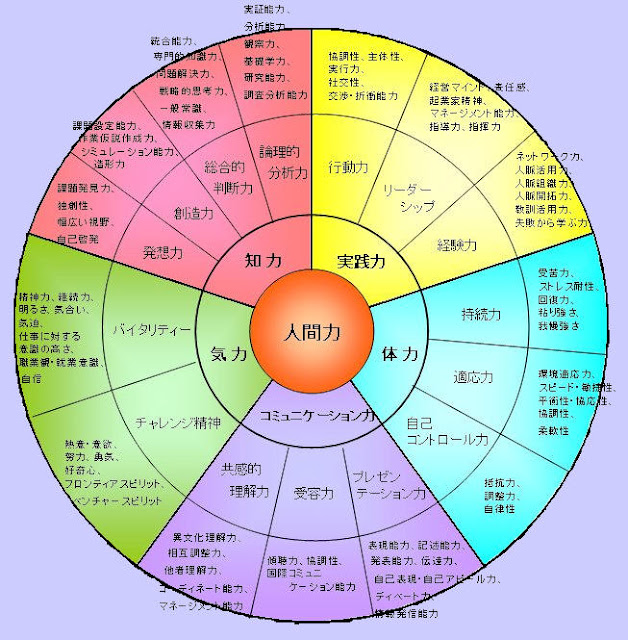


コメント